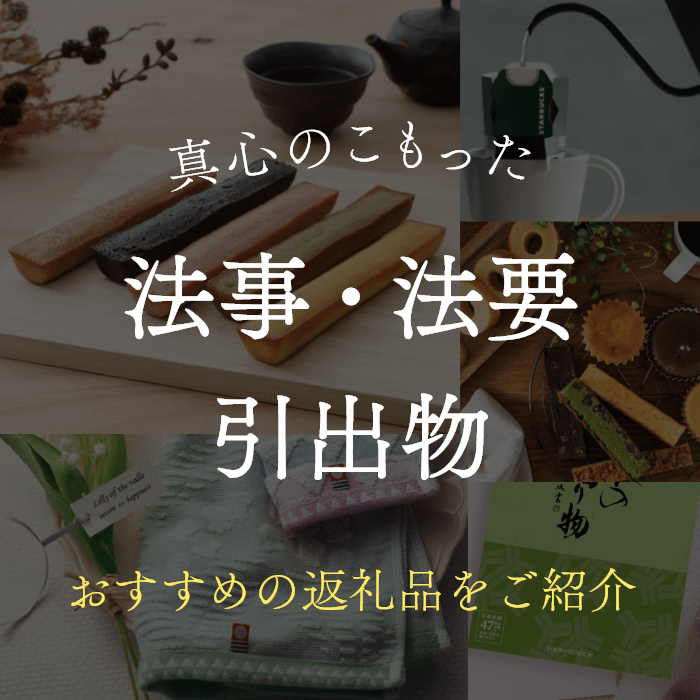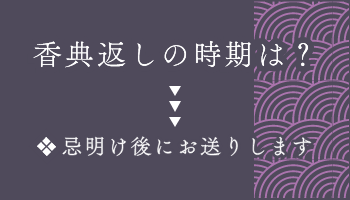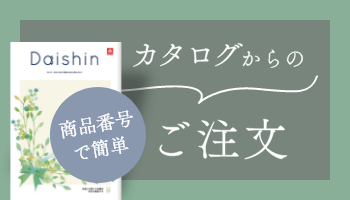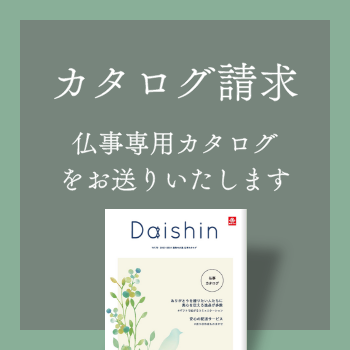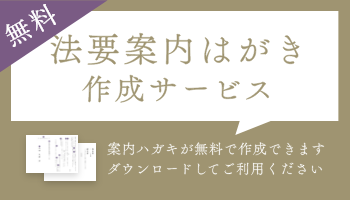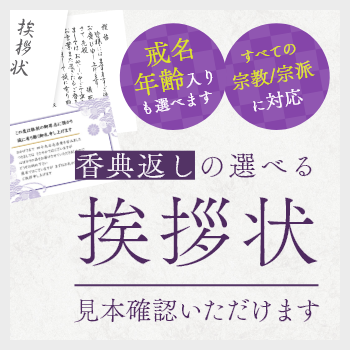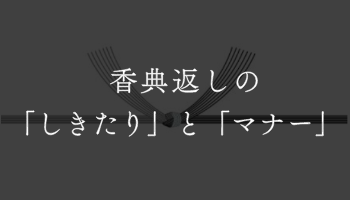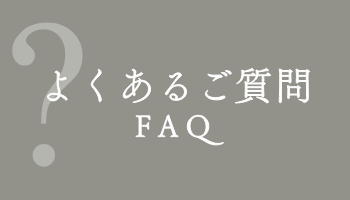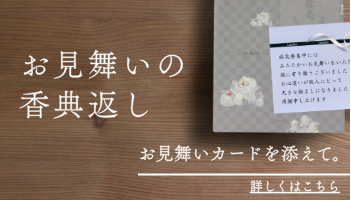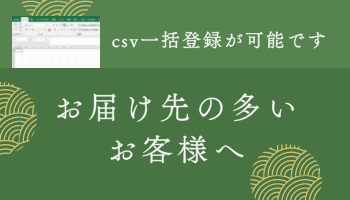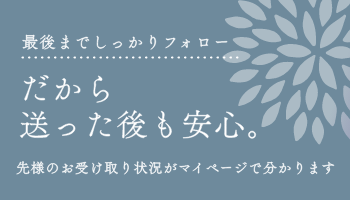よくあるご質問
ご注文について
- 電話での注文はできますか?
- 誠に申し訳ありませんがお電話でのご注文はお受けしておりません。ご面倒でも、インターネットでのご注文をお願い致します。
- 届け先が多いのですが、注文方法はどのようにすればいいのでしょうか。
- 会員登録の後、ログインして頂き、マイページの中にあります「お届け先の多い方へ」をご参照下さい。
お届け先の多い方におすすめのご注文方法
- 追加注文をしたいのですが初回注文の割引率を適用してもらえますか?
- ご注文から7日以内の追加注文は同じ割引率が適用されるお得なシステムを導入しております
<例>最初の注文が108,000円の場合、割引率は20%OFFが適用されます。
追加の注文が10,800円の場合、割引率は通常5%ですが、7日以内の追加注文の場合は最初の割引率20%OFFが適用され、大変お得です。
※7日を越えますと通常の割引率の適用となりますので、予めご了承ください。
割引についてはこちら
- 注文をしたのですが、受付は完了していますか?
- お返しナビでは、注文受付を完了したお客様にご注文内容に誤りがないかどうかご確認をしていただく為に必ず「ご注文内容の確認メール」をお送りしています。
万が一この「ご注文内容の確認メール」が届いていないようでしたら、恐れ入りますがお返しナビまでお問い合わせください。
「okaeshinavi.jp」からのメールが受信できるよう設定をお願い致します。
お届けについて
- お届け日の指定は出来ますか?
- お届け希望日の指定は1週間以降の指定が可能です。注文画面の「お届け希望日」の箇所でご指定が出来ます。
- 自分で作ったメッセージカードを同封していただくことはできますか。
- 大丈夫です。郵送等で以下の宛先にお送りください。ただし、メッセージカードが届いてからの包装になりますので発送日がその分遅れます。ご了承ください。
〒731-0113 広島市安佐南区西原2-20-13
株式会社大進本店 物流センター内
お返しナビ
- 自宅に複数の商品を届けてもらいたいのですが商品の区別は出来ますか?
- 注文画面の連絡欄に「商品ラベル希望」とご記入いただければ簡単に剥がせる商品ラベルをお付けしますのでご安心下さい。
- 注文してから何日くらいで届きますか。
- 通常1週間;10日を目安に最短で発送致します。商品在庫がある商品につきましては3日〜4日でお届けできることもあります。
お届方法はこちら
お急ぎの場合は在庫確認致しますのでお問い合わせください。
お急ぎの方向け「最短当日発送:ギフト特急便」
- お届け先に商品が届いたかどうか分りますか。
- マイページの中にあります配送状況の画面からご確認頂けます。
- お届け先に商品が届いていないようなのですが?
- ご注文受付後、約10日以内にはお届けしております。
2週間を過ぎても商品が届かない場合にはお手数ですがお返しナビへご連絡ください。
※ゴールデンウィーク・お盆・お正月にかかる場合は多少日数がかかることもございます。あらかじめご了承ください。
- 海外への発送は可能ですか?
- 申し訳ありませんが、配送エリアは日本国内に限らせていただいております。
弔事について
- 香典返しの時期は?
-
【仏式】仏式ではふつう四十九日(もしくは三十五日)を忌明けとし法要を営みます。この忌明けを目安にその前後に香典返しを行うのが一般的です。
【神式】神式では三十日祭または五十日祭を忌明けとし、その前後に玉串料のお返し(仏式でいう香典返し)を行うのが一般的です。
【キリスト教】キリスト教式では、特に忌明けの習慣はありませんが、一ヵ月後の召天記念日(カトリックは昇天記念日)の追悼ミサを終えたさい、お花料のお返し(仏式でいう香典返し)を行うのが一般的です。
香典返しの時期についてはこちら
- お墓を建てた時には・・・?
- 墓上げのお供えをいただいた方には、3回忌までは黒白または黄白の水引で表書きを「建碑記念」とし、お返しします。
- 身内に不幸があった年のお中元、お歳暮はどうすれば・・・?
- お中元やお歳暮は、日頃お世話になった方々へのお礼として贈るものです。通常どおり贈ってもかまいません。ただし、忌中(49日)の間は避けたほうがよいでしょう。
- 生前いただいたお見舞いのお返しは?
- お香典だけでなく、生前にお見舞をくださった方には、お見舞いの御礼も一緒にして香典返しをされることが多いようです。
その際には、戴かれたお見舞の半分程度をプラスして下記のようなメッセージカードを添えられますとお気持ちが伝わります。
メッセージカードをご希望の時はご注文の際に、注文途中にあります連絡欄に「○○○○様、○○○○様、○○○○様、○○○○様 にお見舞カード希望」とご明記下さい。
生前のお見舞いのお返しについてはこちらもご覧ください
- 香典返しの相場は?
- 香典返しは、いただいた額の半額が一般的です。
故人の社会的地位や、土地の習慣などで異なる場合もあります。
香典返しの金額/相場はこちら
- 香典返しに相応しい品物は?
- 返礼品には故人の人柄をしのばせるようなものが理想ですが、一般的には、あとを引かないよう、形に残らない消耗品が用いられ、現在では実用品も多く使われます。
香典返しは、どこの家でもよく使う日用品が一般的です。
タオル、寝装品、お茶、砂糖、石けんや供養のお礼を意味するという漆器や陶器などがよく使われます。
会社などへは、全員にわたるように、お茶やコーヒーなどがよいでしょう。
香典返しに相応しい品物はこちらから
お盆提灯について
- 盆提灯は誰が贈るのですか?
- よく親戚が提灯を贈ると言われていますが、最近では喪家がご用意する事が多くなっています。
生前のご恩に感謝する意味で親しい友人やお世話になった方へ贈っても差し支えないようです。
盆提灯はこちらから
- 盆提灯はなんの為に飾るのですか?
- 盆提灯はお盆にご先祖や故人の霊が迷わず帰ってくる目印として飾ります。
盆提灯には迎え火と送り火の役割があり、お世話になった故人の冥福を祈り、感謝の気持ちを表すものです。
- 初盆の家には白い提灯で家紋入りでないとダメと聞いたのですが本当ですか?
柄物の家紋入りを購入したのですがダメなのですか?
- 昔は一年目に白い提灯で二年目以降は柄物に家紋を入れて飾られていましたが、
今では一年目に柄物の家紋入りを購入して永く大切に毎年飾られる傾向もあるようです。
- 盆提灯は宗派によって飾る・飾らないがあるのでしょうか?
- 盆提灯はあくまで先祖の霊が帰ってくるための目印なので、宗派によって飾る・飾らないはございません。
- 盆提灯は一対で飾らないといけないですか?一個だけではダメなのですか?
- 寺院の内陣や仏壇などは左右対称となっており、飾ってある仏具も一対で置くことが基本です。
盆提灯も通常同じ柄を二個セットで飾るのが基本となります。